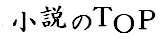|
『マジサイ!』 第参話 ピンチ!? これでサヨナラなの? |
|---|---|
|
「学園長室」と書かれたプレートの掛けてある扉の前に神妙な面持ちで立つ生徒が三人。 近くを歩く生徒たちの視線も、少々痛くなってきた。もちろん、さっきの全校放送で大々的に呼び出しを食らった素子と涼香、それに「付添い人」の未来だ。 「誰が先?」 呼び出されたのは二人しかいないのに涼香が聞く。 「未来」 「ボケないでよね、素子〜。私は呼び出されていないんだから」 「ははははっ」 「じゃ、最初は素子からでいいよね」 と、軽く流して涼香が言った。 「え〜」 「校門は私が先だったでしょ」 「う、うん・・・。仕方ないか」 「じゃ、頑張ってね」 と手を振る未来を、素子はうらめしそうに振り返る。 「お弁当、先に食べててもいいから、私の分、残しておいてよ」 「わかった。また後でね」 ごくっと、つばを飲み込むと、覚悟を決め胸の高さまで上げた手で控えめにノックした。 こん、こん・・・。 「はい、どうぞ」 凛とした声が聞こえてきた。 「しっ、失礼しますっ」 何かの植物の装飾が付いたドアの金具を押すと、重そうな扉は音もなく開いた。 素子は今まで、学園長室に入ったことがなかった。高い天井と大きな窓から入ってくる光がまぶしいぐらいに室内を照らしており、重厚なつくりの応接セットと、壁一面の本棚、歴代学園長の肖像画がはっきりと見える。そして部屋の奥の大きな机の後ろに、ちんまりと座っているのが、このアルレシア魔法学園の学園長であり、二人を呼び出した張本人、三輪皐月だ。 涼香は一週間ほど前に、転入の手続きのために訪れているとはいえ緊張しないわけにはいかなかった。が、覚悟は決めていた。二人は、応接セットの脇を通り抜けると、学園長の机の前に並んで立った。 机の前に立つと、ただでさえ小さい学園長をさらに見下ろすようになる。もし、初めての客が予備知識なく学園長室を訪問し、机に座っている人を見たならば、きっと学園の生徒がいたずらで座っていると思うに違いない。無論、教員用のローブをまとっているので間違われることはないが。 「・・・道成寺素子さん、熊坂涼香さん。あなたたちが今日ここに呼ばれた理由、判る?」 素子にとって理由になりそうなものは、身に覚えがあるだけでも山ほどある。春休み中にソフトボールで割ってしまった窓ガラスのこと、授業中の居眠り、成績のこと、そして、今朝のこと・・・。 まあ、筆記はお世辞にも良い方ではないが、実習の評価はまずまずなので、成績のことではない、と思いたい。第一、成績なら今日転校してきたばかりの涼香まで呼ばれるはずはない。 「『どのことで呼び出されたかさっぱり判らない顔をしていよう』って顔ね、道成寺さん」 素子は、とぼけた顔を必死につくろいながら黙っていた。もし、何かしゃべってしまったらやぶ蛇になるかもしれない。とは言っても、この二人に共通することといったら、やはり一つ。表情とは裏腹に、冷や汗が体中から噴き出している気がした。正直に自首したほうが、処分が軽くなるかもしれないが・・・・。 「じゃあ、お待ちかねの再現映像を見てもらおうかな。美貴さん、カーテン閉めて」 隣に立っていた、副学園長の氷室美貴が壁のボタンを押すと、大きな窓にカーテンがゆっくりと引かれていった。太陽の光が、だんだんと細くなっていき、ついに部屋は真っ暗になってしまった。 学園長は、部屋が真っ暗になったのを見届けると、机の中からソフトボールぐらいの水晶球を取り出し、力を込めた。 「クリスタヴィジョン!」 皐月が唱えると、水晶球は輝き始め、部屋にいる四人の顔を青白く照らしていく。部屋中が、まるで冷たい海の中にいるかのように青の中に沈んでいった。その球体から流れ出す光も、やがて一点に収束し始め、球の頂上にすべての光が集まった瞬間、天井に今朝の光景が映し出され始めた。ちょっとした映画のようだ。シーンは素子が助けに来たところから始まり、魔物を倒して学校に向かうまでである。本人たちも手一杯だったため覚えていないような戦いの細部まで丁寧に見ることが出来る、抜群のカメラワークだった。 「どう?感想は」 皐月の満面の笑みが、二人には痛かった。ここまで見せ付けられてしまったら、言うことなどひとつも残っていまい。すべては水晶球の映し出したとおりである。すべてを映し終わると、水晶球の光は止み、部屋は再び静かな闇の中に戻った。 「カーテン、開けてもらえる?」 カーテンが、また両脇に引っ込んでいく。窓に正面を向けている二人には、太陽の光がまともに差し込んできてまぶしかった。先ほどまでスペクタクルを上映していた水晶球はまた一個の鉱物にもどり、学園長の顔を上下逆さまに描いている。 「で、あなたたち、自分のしたことが分かっているでしょう?」 と皐月が二人を交互に見つめた。 無免許封印。例外なく、処分が下る唯一のケース。良くても停学。もし悪ければ、せっかくここまで学んできた神ヶ丘から追放。 素子は、今朝、自分を見送ってくれた母親の顔を思い出していた。 「お母さん、悲しむかなぁ」 背中に溜まった冷や汗が、雫になって流れていった。ちょっとやり過ぎてしまった。素子にとって「やり過ぎて」しまうのはいつものことだが、今回はあきらかに重大な校則違反である。 「済みませんでした!」 大きな声に素子は我に帰った。自分の横に立っていた涼香が、頭を深々と下げていたのである。涼香の長い髪が、滝のように垂れ下がっている。表情は分からないが、微動だにしない背中が、素子には何よりも雄弁に思えた。 「本当に済みませんでした!」 素子も、涼香に続いて頭を下げた。 「わたしが悪いんです。わたしが。わたしが、最初に封印しようとして、魔法を使ったんです。で、途中で道成寺さんが助けに入ってくれて、それで・・・・」 「それは先ほど、水晶の映像で見ました」 「道成寺さんは何も悪くありません」 「そうね」 あっさりと「そうね」と返した学園長を、二人は思わず顔を上げて見てしまった。 「道成寺さんは悪くないんでしょ?熊坂さん」 「は、はい・・・・・」 物分りが良いのか悪いのか分からないが、学園長はちょっととぼけたような顔をして涼香を覗き込んでいる。皐月の瞳からは何も読み取れなかった。学園長は当惑する涼香から素子に向き直った。 「道成寺さんは、何か言うことある?」 「あ、あの・・・。熊坂さんだって何も理由がないのに魔法を使ったりはしません。ゼッタイ、わけがあります。それに、最終的に封印をしたのは私です。熊坂さんだけに処分を下すのはおかしいです。処分を下すなら、私にも!」 学園長は、机に載ったままの水晶のような目で、二人を見ていた。素子は、自分の心の中まで、その目に映し出されているような心地がした。 やがて三輪皐月は、二人から視線を外すと、机の引き出しの中から紙切れを二枚取り出した。A4サイズの厚めの紙で、学園の紋章の透かしが入っている、正式な文書を書くためだけに使っている特別な紙だ。む?正式な書式、ということは「放校」ということなのだろうか・・・・。涼香をチラリと見た素子は、さっきまで気丈に学園長に話していた彼女の目に、涙が溜まっているのに気づいた。いくら何でも、わけも聞かずに放校処分なんてあんまりだ。素子は学園長を見損なった。 学園長は、一呼吸置くと、もう一度二人を交互に眺めた。そして大きく息を吸い込んだかと思うと、 「おめでと〜!」 身構えていた二人は、まるで大きな発見をした子供のような笑顔の皐月に、すっかり肩透かしを食らってしまった。 「ちょっと驚いたでしょ。そんな怖い顔しないの。あなたたちは『世界魔導学連盟』の規定を満たしたと認められましたので、ここに封印許可証とともに初級封印士の称号を与えます。私立 神ヶ丘魔法学園 学園長 三輪皐月」 「それって、学園長・・・」 「そう。許可証。二人とも3月に受けた初級封印士の資格試験に受かっていたんだよ♪。だから、成績を先取りして、ここで発行しちゃおうってわけ。本当なら合格者は面接のあと6月ぐらいに授与式があるんだけど、今回は」 「じゃ、いまのが?」 「そう。その面接の代わり。で、二人とも合格!封印士になるにはもってこいの人材よ。特別に今日発行の封印許可証を出すから、今朝のことはナントカなるわ。うん」 「やったー」 「やったねー。素子!」 「退学にならずに済んだ!しかも封印士の免許まで!学園長、大好き!」 「ありがとうございますー」 「でも、若いからって何でも許されると思ったら駄目だよ。若いと思っていても、すぐに年なんてとっちゃうんだから」 年なんてとっちゃう、と言っている本人が、一番年を取っていないように見えるのが、二人にはおかしかった。 「お二人とも!でも、それはあくまでも学園の外に今回の騒ぎを広げないための、苦肉の策なの。学園としても示しをつけるためには、何かしらのタスクをこなしてもらわないといけませんわ」 幅の細い眼鏡をかけた氷室が、はしゃぐ二人をたしなめる。 「たすく?」 「そうです」 氷室は学園長を促した。 「そうそう。あなたたちにやって欲しいのは、『封印部』を作ってもらうこと」 「封印部?そんな部活、いま学園にありましたっけ?」 「ないですわ。今はね。でも、あなたたちには新しい部として作ってもらいたいの。それが、今回の事件を見逃す引き換えとしてのワークになる。断ることは出来ないわ」 氷の女、の異名は伊達ではない。氷室は表情ひとつ変えずに二人を試している。 「なーんだ。そんなことか。それならいいです。やります」 「私も、やります」 「そんなに簡単に決めてしまってもいいの?二人とも。何をやるかすら聞いていないのに」 「だって、これからも神ヶ丘にいれるんだし、何でもやります。それに封印部って響きが面白そうですし」 「断ることが出来ない、後ろに下がれないなら前に出るしかないでしょう?副学園長」 少し呆れ顔の氷室を尻目に、皐月は大喜びだ。 「それでこそ封印部!二人にお任せしちゃうね。活動内容は・・・・」 「内容は・・・・」 「そんな大した事ではないんだけどね。封印とか魔法に関することは何でもやろうって感じの部活。部長は・・・・・。じゃあ、学園にいる時間が長い道成寺さんでいい?」 「私はいいです。今日来たばかりで何も分からないし」 「私でいいんですか?」 「不満なら熊坂さんにやってもらうけど」 「いえ!やります!やらせてください!」 初めからそう言えばいいのに・・・・・、と涼香は素子の必死な顔を見て思った。 「あ、そうそう。二人とも知っているとおり、この学園の部活って、部員が5人いないと創部できないのよね。10日以内にメンバーが集まらないと、」 「集まらないと、どうなるんですか?」 「廃部」 「廃部ということは・・・・・?」 「タ・イ・ガ・ク、かもね〜」 「だって、さっき学園長が許可証をもらって・・・・」 「それはそれ、これはこれよ。あなたたちが魔法を使ったのは、その証明書と小さなカードを受け取る前でしょ?いつ私が渡したか、なんて何とでもなるし」 皐月の顔が、小悪魔のように見えた。 「あの、集める部員って、誰でもいいんですか?」 涼香が冷静に聞いた。たしかに5人集めるとなると、これは重要な問題だ。 「よくなーーーい!だって、封印部の部員にふさわしくないと、封印部を作る意味がないでしょ?」 「・・・・・ふさわしいかって、誰が決めるんですか?」 「もちろん私、三輪皐月が決めます。10日後、集まったメンバーを見て決めるの。大丈夫!あなたたちがその気になれば良いのが見つかるから」 「ただし、運がよければね」 最後に氷室の一刺し。 「・・・他人事だからってお気楽・・・・・だよね」 素子が涼香に耳打ちした。 「あ、忘れてた。これが封印部の部室の鍵ね。場所は、本館アネックス2階の一番奥。封印部って書いてあるからすぐ分かると思うよ」 キンコンカンコーン 「あ、昼休み終わりね。ミキティー、学食に食べに行こっか」 「そうですわね。一仕事終わってほっとしましたわ。もう二人とも帰っていいわよ。10日後が楽しみね」 立ち尽くす素子たちを置いて、二人は学食に行ってしまった。 「しまった!お昼ごはん食べ損ねた!」 慌てて学園長室を出た二人を、心配そうな顔をした未来が迎えてくれた。 「さっき学園長と副長が出て行ったからどうなったか心配していたんだけど・・・大丈夫だったんだね、素子!」 「わかる?そのとおり。大丈夫でした!」 宝くじが当たったとしても、ここまではないぐらいの笑顔をした素子を、一目見れば誰だって大丈夫だってことは分かる。 「良かったー。熊坂さんも?」 「私も、素子も処分なし!あ、素子、第一メンバー発見ね」 「え?何、それ?」 第一メンバーといわれた未来は、素子に尋ねた。 「詳しいことは後で話すから、はやく教室に戻らないと授業始まっちゃう。未来、なにか食べる物ある?」 「うん。購買でおにぎりを買って置いたから、教室に戻る前に食べちゃいなよ」 副学園長、氷室美貴は今回の一件をなんとか処理でき、学園の名前に傷が付かなかったことに安堵していた。その上、懸案だった「封印部」の創部問題も、一気に片付いてしまった。生徒が教室に戻ってしまってがらんとした廊下を歩きながら、素子と涼香の事を思い出していた。 「あの二人に任せて本当に間違いないのでしょうか、学園長」 「大丈夫よ。あの魔法のキレと瞳を見れば、彼女たち以外にはありえない。そう感じた。それは紗弥さんだって同じ意見だったはずよ。そうだ、今日はミキティー何食べるの?」 「私はA定食にしますわ」 「じゃあ、B定食にしようっと」 「食後にも仕事が残っているんですから、午後のお茶しに抜け出しちゃ駄目ですよ。それに、私がさっきから気づいてないふりしているのをいいことに、ミキティーって呼ばないでください学園長〜」 「ギクッ。わかってるよ、みきてぃー!」 つづく | |