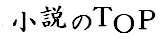|
『マジサイ!』 第弐話 YOKOSO!神ヶ丘へ |
|---|---|
|
「あちゃー。葛城先生だよ」 素子は桜並木に隠れながら、校門の様子をうかがってみた。 「見せて」 「そおぉっと、だよ。気づかれないようにね」 50メートルは離れているから絶対に聞こえるわけがないのに、思わず二人とも声を抑えて話してしまう。 涼香が覗くと、水色のジャケットを着た若い女性が門の脇に立っているのが見えた。どうやら大きな門の脇にある小さな通用口で、遅刻してきた生徒を待ち構えているらしい。 「あんまり見ると気づかれちゃうよ」 涼香は、また桜の陰に引き戻されてしまった。 「どう?見えた?」 「門は見えたけど」 神ヶ丘魔法学園の正門は、高さ3メートルぐらいで、鉄の柵のようになっており、中央には学園の紋章が入っている。とても頑丈そうだし、飛び越えるのも無理だ。 「どうやって入ろうか・・・」 「ちゃんと事情を説明すればいいじゃない。『魔物を倒していたので遅れました』って」 「わ、わ、そんなこと、ねぇ。あんまり言いたくないじゃない、ほら、いかにもーって感じだし」 「急にあせって、どうしたの、素子?」 「別に・・・。それよりもどうやって中に入るかが問題よね。やっぱり私の『抜け道』を使うしかないかな。いくつか先生に見つからないで入る方法があるんだけどって、熊坂さん、熊坂さん!?あ、ちょっと・・・、ねぇ」 見回すと涼香は、勝手に校門の方へすたすたと歩き出していた。 「あ、熊坂さん・・・」 慌てて素子も追いついた。涼香は物怖じせず、まっすぐに歩いていく。門と教師が近づいてくる。近くで見る彼女は、思っていたより背が高かった。 「おはようございます」 涼香が先に挨拶。 「おはようございます」 素子も間髪を入れずに続く。 「おはようございます」 思っていたよりも高い、透き通った声だった。 「登校時間はもう終わってしまいましたが、今日はどうしましたか、道成寺さん」 葛城先生は涼香の後ろになかば隠れている素子に言った。 「あの、じ、実は・・・」 「私、今日から神ヶ丘魔法学園高等部に転入してきました熊坂涼香です。通学路に魔物が出たので、途中で会った道成寺さんに案内してもらって回り道をしてきました」 と、涼香が助け舟を出すと、 「そうです。そうなんです。道を歩いていたら魔物が大暴れしていたので、ちょうど道に迷っていた熊坂さんと一緒に回り道をして来たんですが・・・」と、葛城先生の表情を窺うように、素子が言った。 先生の態度には何の変化もなかった。反応が全くない時、それを待つまでの時間はたとえ一瞬でも長く感じられる。 「・・・・いいでしょう。そういうことなら仕方ないですね。もう全校集会は始まっているから、後ろの方に並びなさい」 先生は、通用口の鉄扉を開けた。扉は、すこし軋みながら、ゆっくりと片方だけ動いた。 「どうして、ウソついたの?熊坂さん」 門から入ってしばらくしてから、素子が不意に聞いた。 「ウソって、何のこと?」 「ほら、魔物にあって『回り道』してきたって」 「でも、まるっきりウソってわけでもないでしょう?」 確かに。涼香の言ったことは、ウソではない。涼香はちょっと思い出し笑いをしながら素子の目をのぞきこんだ。 「まあ、そうなんだけど。でも、そうじゃなくって、どうして本当のことを全部話さなかったのかなって思って」 「だって、素子、許可証をもっていないんでしょう」 「え!?なんで知ってるの?」 今朝初めて会ってから一時間も経っていない人から、自分のことをズバリと当てられて、素子の声は裏返ってしまっていた。封印を行うためには、封印者の証となる「許可証」を持っていなければならない。これは、「世界魔導学連盟」の認める資格で、持たない生徒が封印を行った場合は、どんなに良くても停学。悪ければ放校処分、魔法業界からも追放となる、とても厳しいシステムなのだ。 「そんなの、すぐ分かった。だって、持っていたら堂々と『封印していました』って言うに決まっているじゃない。なのに抜け道とか抜け穴とか言うから」 「ありがとう・・・・。口裏合わせてくれて」 「別に口裏合わせたわけでもないんだけどね」 「ってことは?」 「私も、だから」 涼香はちょっといたずらっ子のように、舌をぺろっと出した。 「ということで、今年も皆さんの活躍を期待しています。よく学び、よく遊んでねっ」 二人が校庭に出ると、壇上には誰もいなかった。神ヶ丘魔法学園長、三輪皐月の「なが〜いお話」が終わってしまったようだ。 「あ、もう終わっちゃった。聞きたかったな」 「学園長の話のこと?」 「うん。学園長の話って、結構面白いんだよ。長いけど、楽しみにしている人って、多いんだ」 「そっか・・・。なんだか、変わってるね」 「そうかな。あっ。熊坂さん?」 「涼香でいいよ」 「うん、じゃあ涼香って呼ぶね。涼香?」 「なに?」 「何組?」 「3組」 「なんだ、早く言ってくれればいいのに。一緒の組だよ。ほら、ここ。ここの後ろに並んでおこうよ」 二人は、全校生徒の中に加わると、すぐに溶け込んでいった。 学園長室で堂々とお茶を飲んでいるのは、クラシカルな黒ローブを着た中等部の生徒・・・ではない。たった今、全校集会から戻ったばかりの三輪皐月である。ちっこくて童顔なために、どこから見ても中学生。しかも年齢は非公開、前歴も不明なため、本当に10代前半だという噂もあるが・・・・。 猫舌なのか、しばらく熱い緑茶に苦戦していると、デスク上の内線電話が鳴った。 「こんな時間に誰だろう〜って、もしもし」 「受付です。警察の方が、学園長にお話がある、ということなのですが」 受話器を持つ手が、一瞬震えた。 「わかったわ。お通しして」 手の震えは、声に全く伝染しなかった。むしろ学園長の声は、凛とした、大人の声に変わっていた。 「まったく、早いんだから・・・・」 学園長は、デスクの上においてあった水晶球を引き出しの中にしまうと、もう一口お茶をすすった。 「入りますよ、学園長」 入ってきたのは、一時間前に素子と涼香が「封印」した現場を調べていた、黒いスーツを着込んだ二人組みだった。 「久しぶりですねー、織田警部」 学園長は親しげに、二人組みのごつい方へ声をかけた。 「久しぶり、というほどの久しぶりでもないでしょう。先月会ったばっかりだ」 勝手に学園長室のソファにどかりと座り、ポケットからからタバコを取り出した。 「ここは禁煙ですよ、警部」 「おっと、ついいつもの癖でね。じゃあ、早速本題に移るとしましょうか。柴田君、あれを」 柴田刑事がブリーフケースから取り出したのは、現場で採取した試験管だった。中には、毛のようなものが入っている。 「これ、分かりますよね。魔物の痕跡。しかも、ついさっき封印されたばっかりの。でも、おかしなことに、『封印者』の封印影が無かったんですよ。許可証を持った者が封印した際に残さなければならない封印者の印がね」 「ギクッ」 学園長は、視線を校庭の桜に移した。 「この封印した人、今日に限ってカードを忘れたんでしょうかねぇ。それとも・・・・モグリだったのかなぁ。ねえ、三輪学園長」 「そうね、きっと忘れたんじゃないの?」 「ふふっ。あなたは昔から嘘をつけないですね。嘘をつくときには、いつも鼻の横をかくでしょう。本当は知っているんでしょ、誰が封印したか」 「ううぅ・・・。でも知らない。知らないものは知らないっ」 と、今度は子供が駄々をこねる様に両耳をふさぐ。 「学園長、私もここのOBですからあんまり強いことは言いたくないんですよ。でも、規則は規則だし、生徒に何かあってからじゃ遅いんですよ。強すぎる炎は、自分自身を焼くことになりかねない・・・。特に、今回の件で魔物を封印した生徒は」 「・・・・・」 学園長は、上目遣いで織田警部を見つめた。瞳には、すこしだけウルッと涙が・・・・。 「・・・・・ふぅ。分かりました。分かりましたよ。そんな目で見ないでください。今日のところは、これで帰ります。でも、こんなことがまたあれば、学園の信用問題にもなる。私にもかばいきれなくなりますよ」 織田警部は、柴田刑事に合図をすると、そのまますぐに学園長室を後にした。 「あちゃ〜。あの子達、やってくれちゃったわね」 「しかも、派手に・・・」 入ってきたのは、キャリアウーマン副学園長の氷室美貴だ。いつも冷静な彼女は、学園長のよきパートナーでありお守り役であるし、彼女の経営手腕がなければ学園もここまで発展できたかわからない。 「美貴さん、知っていたの?」 「知っていたの、って私が教えて差し上げたんじゃないですか〜。覚えてますか〜〜」 「うん。覚えてるって。ホントホント。でも、よりにもよって、こんな日に事件を起こさなくってもよかったと思わない?ミキティー」 「ミキティーって呼ばないでくださいよ、学園長。それは置いておいても、むしろ今日だから助かった、という考え方も出来ますわ」 「確かにね。急に言っても、絶対断られたと思うしね〜。昼休みに、呼び出しをかけるしかないかな」 全校集会が終わったあと、涼香は担任の有明先生と一緒に職員室に向かった。一方の素子は転校生と登校してきたことで、クラス全員から(特に男子から)質問攻めにあっていた。名前、どこから来たか、どこに住んでいるのか、誕生日はいつか、好きな花は、彼氏はいるのか・・・・。 「みんな、私も初めてなんだから、詳しいことは知らないよ。もうすぐ本人が来るから直接聞いて」 「でもさ、ちょっとキレイすぎるっていうか、なんか話しかけづらいっていうか」 「そうそう。モデルみたいだよね、今度の転校生。さすがシュルベールって感じでさ。制服も緑のエレガントでシック、だしね」 「だから、ほら、まずは道成寺がさ」 「おーい、来たぞ」 ドアに張り付いていた見張り役が知らせると、素子の周りに集まっていたクラス全員がいっせいに着席した。心なしか、男子生徒の落ち着きがなくなっているような気がする。いや、男子だけではない。女子もだ。普通なら、こんな美人が転校してくるとなったら、やっかみ半分の視線になるだろうが、不思議とそういった空気は無かった。 廊下に足音が二人分聞こえ、しばらくするとドアが開いた。有明先生と、柔らかく長い髪を二つにまとめた女子生徒が入ってきた。彼女が歩くたびに髪の先がふわりと揺れ、いい匂いが教室中に振りまかれるような心地にさせるが、前を歩く有明先生の濃いひげの剃り跡とジャージ姿でその雰囲気も「中和」されてしまっているのが惜しかった。先生はいつもの通りどでかい声で「おはよう!」と挨拶すると、クラス中を見渡してから名簿を机の上に置いた。 「えー。今学期から、この3組に転入することになった、熊坂涼香さんだ。熊坂さんはEUのソールズベリー魔科学院からきた帰国子女だが、日本語は問題なくできる。帰国子女だからって、みんな、英語の宿題をやってもらおうなんて考えないように!特にそこ!春休みの授業を受けたのを忘れちゃ駄目よ!?うん。じゃ、熊坂さん、自己紹介を。みんな、拍手〜。」 「今日から神ヶ丘魔法学園に転入することになりました、熊坂涼香です。転校生といっても、小さい頃はこの町に住んでいました。また帰ってこられて、魔法の勉強も続けられてとてもうれしいです。みなさん、いろいろと教えてください。よろしくお願いします」 「では何か熊坂さんに質問は?」 有明先生が教室を見渡す。 一瞬の沈黙のあと、教室内には成真山の林のように、たくさんの手が挙がっていた。 「誕生日、いつですか!」 真っ先に手を上げた男子生徒が勢い込んで質問する。 「6月2日です」 「この前、授業でやった占星術でも試すのか?そりゃ勉強熱心だねぇ」 と、先生がつっこむとクラス中が笑った。笑いながらも何人かはキチンとメモを取っているのが見える。 「何か趣味はありますか?」 「特にないですけど・・・。オペラとかクラシックが好きでよく聞いています」 おー、というため息とも付かない声と、さすがヨーロッパ帰りだ、という声が入り混じった。 「はい!そこまで。またあとで、あらためて聞くこと!熊坂さんは、空いている席にすわって。今は出席番号順だが、近いうちに席替えするぞ」 席替え、という単語が出た瞬間、涼香から遠い席に座っていた男子数名が歓声を上げた。 「うるさーい!じゃあ、一時間目は魔学史だから、続けて授業にはいるぞ。高等部になってからの第一回目は『マナ』の発見と活用法を発明した魔学者・・・・・」 午前の授業はあっという間に過ぎ、(決して眠っていたわけではない)、待ちに待った昼休みになった。 「ねぇ、涼香。今日のお昼、どうする?」 神ヶ丘のランチタイムは、学生食堂かお弁当。6割ぐらいの生徒が学食を利用している。 「お弁当は持ってきていないから、食堂で食べるつもりだけど・・・」 「じゃ、ちょっと待ってね。もう一人呼ぶから」 というと、素子は教室の窓側に座っている、ボーイッシュな短髪の女の子を呼んだ。 「ミライ〜。お昼、食堂で食べない?」 「いいよー。熊坂さんも一緒でしょ?」 「そう。じゃあこっちに来て」 ミライ、と呼ばれた子は、カバンからランチボックスを取り出すと、涼香の席まで来た。 「えっと、こっちは私の幼馴染の未来」 「野々宮未来です。よろしくね」 「はじめまして。いろいろ教えてね」 「じゃあ、校内の案内を兼ねて、行こっか?」 久しぶりの校内は、なんだか面白い。神ヶ丘は中高一貫校なので学年のメンバーが変わらない上に、クラス替えは2年に一回なので中3と高1は同じクラスメートに同じ担任。だから何だか高等部に進級したという実感が薄いし、髪を切った後みたいな居心地の悪さがあると思う。 友達が高等部用の制服を着ているのもコスプレっぽいし、教室は中等部の新館から21世紀館に変わっているのも落ち着かない。それに校内には新しく入学した、知らない中等部一年生達が走り回っている。いつも来ている学校だって、少しずつ変わって行く。そして、ここからも見える校庭の桜。本当に、もう一年経ってしまったことを実感した。 校内を涼香と歩いていると、すれ違う生徒に振り返られたり、ずっと見られていたりしていることに気が付いた。さすがに新学期でも、他校の制服を来て校内を歩いている人は、そうそういない。 「そういえば、どうして神ヶ丘の制服じゃないの?」 ミライが涼香に聞いた。 「制服ね、サイズが無かったから時間がかかるって言われたんだ」 「そっか。あんまりサイズなさそうだからねっ」 素子はあらためて涼香の全身をチェックしてしまった。クラスの男子が言っていたように、モデルのように背が高い。その上、出るところは出ているし、引っ込むところは引っ込んでいる、まことにうらやましい体型だ。モデルとか芸能人だといっても通じるかもしれない。何かのオーディションにでも、内緒で出してみようか、と素子は思った。これでは、ソールズベリーにはサイズがあっても神ヶ丘では絶対に見つからないに違いない。 「ね、涼香?」 「どうしたの?」 「さっきから気になっていたんだけど、どうしてあそこで封印しようと思ったの?」 「封印って何のこと?」 今朝の一件を知らないミライが聞いた。 「あ、あのね、なんか言ったっけ?私」 「とぼけないでよね、素子〜〜〜」 「ぜんぜん、とぼけてなんかないよ」 「だから、封印って・・・・・」 「神ヶ丘魔法学園のみなさ〜ん。いよいよ待ちに待ったお昼の友、一日一回のココロのオアシス、カミガオカン・ラジオの時間がやってまいりました。本日も、ビシバシやっていきまーす」 質問の最後をさえぎる様に、お昼の放送が学園内に響きだした。 「あ、これ面白いよ。いろいろ学園内のこととか、分かるし。学食で聞こうよ」 学園内に詳しい素子が、涼香にレクチャーした。 「パーソナリティーはお馴染み月曜日の嵐山みずほです。あ、今日は始める前にお知らせがあります。高等部1年3組の道成寺素子さん、熊坂涼香さん、至急学園長室まで来てください。繰り返します高等部1年3組の道成寺素子さん、熊坂涼香さん、至急学園長室まで来てください。では、今日のラジオ、始まりまーす」 「いま、何か呼ばれたような気、しない?」 「やっぱり、私たちの名前だったよね・・・・。ってことは・・・・・」 「えーーーー!!」 「えーーーー!!」 二人の声はぴったり重なっていた。 つづく | |