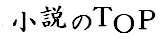|
『マジサイ!』 第壱話 出会い!?桜の木の下で |
|---|---|
|
重そうな扉。 がっしりしていて、埃や汚れがこびりついて。 扉のいろいろなところについている飾りだって昔は金色だったはずなのに、今はメッキが剥がれて緑色になりかかっている。でも、どこかで見たことがある。 そう、学校だ。本館の2階にある「開かずの扉」。誰も開けたことがない学園の七不思議。肝試しの時は、ここのドアノブにカードを入れた袋を下げておく。一人で真っ暗な廊下を渡って、カードを一枚ずつ引いて帰ってくるのだ。みんな、明るいときでも近寄りたがらない。この部屋の前に来ると、いつも何かが中で動いているような気がする。 そう思って立ち去ろうとしたときだった。 「素子ぉ・・・」 低く、くぐもった声がしたような気がした。 「誰・・・・・?誰か私のこと、呼んだ?」 「素子っ・・・」 今度は別の声だ。最初よりも高い、女性の声だ。 「どこ?」 「素子・・・」 振り向くと、「開かずの扉」のドアノブが、暖炉の薪のように赤く輝きだした。見る見るうちにその光は、揺らめきながら全体に伝わっていく。さっきまで埃まみれだった扉は、溶鉱炉のような真の熱さを一面に放って燃え出した。 「扉をあけ・・・」 「うわぁっ」 目が覚めた。 「素子〜。起きているの。遅刻するわよ〜。素子ぉ」 「今何時〜?」 「時計見なさい」 7時45分・・・・し、しちぢよんじゅうごふん?うわぁ。 「なんで起こしてくれなかったの!?」 「何回も起こしたわよ〜」 ベッドから飛び起きると、急いで身支度を整えた。高等部の入学式になのに、しょっぱなから寝坊してしまうとは。 「今日は、入学式だから、はやく起こしてっていったのに〜」 「だって、あなた中等部からエスカレーターであがるだけって言ってたじゃない。入学式って言ったって、大したこと無いって」 「なんだって、初めが肝心でしょう?じゃ、いってきます!」 「素子、これ。おにぎり!」 「サンキュ!」 「いってらっしゃい。気をつけて」 家を出たのが8時。バスに乗れたら、ほぼギリギリで間に合う、と思う。でも、バスを逃したら全速力で学園まで走るしかない。 「もう・・・。今年中には魔法器の免許とってやるぅー」 幹線道路に出て、右手を確認。と、緑色の車体が坂をのぼってこちらに来るのが見える。あれを逃したら大変だ。バス停までスパートをかけ、ゴールしたのと同時にバスも止まった。 「ラッキー。助かった!」 額から落ちる汗を拭きながら、素子はバスに乗り込んだ。一息ついてから周りを見渡してみる。そこそこ混んではいるのだが、案の定、こんな遅刻間際のバスに乗っている生徒は一人もいない。これは、本当に新学年早々遅刻になるかも、と素子は焦った。とは言ってもバスに乗ってしまった以上、どんなに心配しても遅刻するときは遅刻する、と思い直してカバンからHDプレイヤーとおにぎりを取り出した。 バスが大きな川を渡りきると、ようやく学園のある成真山区域に入る。山といっても、丘ぐらいの高さしかないが、面積は広い。裾野には数軒の民家があるものの、上っていくにつれ学園と関連施設、マナ発電所などの公的な施設しか建っていない。その他には本当に何もないから、緑が多く空気のおいしい所だ。バスは丘の中腹にある学校前を通る。いつもの時間に、規則正しく動くバス。あとは、30分の閉門までにつくはず、だ。 素子は、目の前の空いた席に座った。桜並木が窓枠いっぱいに広がった。緩やかで長い上り坂になっていて、この季節になると、ちょうど桜のトンネルの中をバスが進んでいく、ちょっとした名所になっている。中等部からいたから、この桜を見るのも4回目だ。 素子は、桜吹雪を見ながら今朝見た夢を、ふと思い出していた。開かずの扉。顔に熱まで感じたように思えた、あの炎。自分を呼んだように聞こえた声。 「ま、あの声はお母さんだとしても、扉かぁ。トビラ・・・。やっぱり開かずの扉かなぁ」 しかも、よく聞くような「枕元に霊が立っていて宝物を教えてくれる夢」だったとしたら。誰も知らないあの部屋には、何か学園の秘密のお宝物が眠っているのかもしれない。とんでもなく重要な魔法具とか・・・。 「魔法器だったら私がもらっちゃったりして・・・。なーんてね」 キキィ―――― 素子も乗客も、前につんのめってしまった。 「なんなのよ〜、もう。遅刻するじゃない」 遅刻ギリギリで飛び出してきたことを棚に上げて、素子は運転席の方をにらんだ。いや、バスに乗っていた全員が運転席をにらんだ。 「お客様にお知らせします。お急ぎのところ大変申し訳ありませんが、只今、進行方向に魔物が出現した模様です。通行できませんのでUターン致します」 小心者そうなバスの運転手が、本当に申し訳なさそうに、車内にアナウンスした。 「やった・・・。これで『遅延証明書』をもらえれば堂々と遅れられる!」 魔物が現れるのは、ほとんど学校とその周辺部に限られる。とはいっても、まだここは山の裾に近いので、めったに凶暴な魔物はいないはず。だから魔物でバスが遅れる、というのは一年に一回あるかないかの珍しいケースだ。通常は、「封印士」の資格を持った人が来て、すぐに封印するから何の問題もない。ただ、安全のためバスや車は引き返すか、避難しなければならない。 「Uターンします」 ぼんやりと外を見ていた素子の目に、次の瞬間、道路の真ん中に立つ緑色の人影が飛び込んできた。かなり遠い所であったが、それは小山のような黒いカタマリの周りを飛び跳ねている。誰かが魔物と戦っているに違いない。 素子は緑色の影を注意深く見た。 「ま、まさか」 ―――――ピ−ンポーン―――― 「降りま〜す」 バスの奥から女子高生が一人、人をかき分けながら出口まで来た。 「でもね、今はね」 「早く!降ろしてください。学園の生徒ですから、大丈夫です」 「そう?じゃあ、開けるよ。ホントに開けちゃうよ」 ドアが開くが早いか、全速力で目の前の並木道を走っていった。 「よし」 と素子が言ったその瞬間、満開の桜の木が、ピンクの軌跡を描いて青空から降ってきた。乗客たちから悲鳴があがった。桜はバスのすぐ後ろを走りはじめた彼女を直撃したからだ。 「まったく、いちいちつきあっていられないよ」 花の中から声が聞こえた。 そして、真っ二つに切られた桜の木の間から、遠ざかっていく彼女の姿を運転手と乗客は見送ったのだった。 太刀を召喚した素子は、通学カバンを路肩におくと、スカートを軽く押さえながら車道をぐんぐん駆け上っていく。少しずつ二つの影がはっきりした形になってきた。やはり素子が思ったとおり、緑色の影は、どこかの高校の制服を着た背の高い女の子で、黒いのは魔物だった。 落ちたら20メートルはある断崖とコンクリートに覆われた絶壁に挟まれた「桜坂」で、魔物が満開の桜並木を頭に生えた角で次々に吹っ飛ばすたびに、あたり一面に桜吹雪が舞い乱れる。女の子は桜のブリザードの中、飛んでくる大木を最小限の動きで巧みにかわしていた。 「あなた、誰?」 魔物から視線をそらさずに、彼女は言った。攻撃を避けるたびに、キレイに手入れされた長い髪が、風にふわりと舞う。 「助けに来たのよ」 「助けるつもりなら、邪魔にならないところにいて」 業を煮やした魔物は、頭に生えた角を前に突き出すと、一気に女の子へ突撃していった。 「アクエラカーテン!」 そう叫ぶと、地表から瞬間的に噴出した水が滝の幕になって彼女を覆う。それでも魔物はスピードを緩めない。 「危ない!」 幕は、魔物の前にあっけなく破けた。魔物はそのまま突進し続け、道の横に切り立った崖へ頭をめり込ませてようやく止まった・・・。いままで魔法の幕があった場所は、魔物が踏み荒らした跡しか残ってはいなかった。 素子は、動けなかった。 が、すぐに我に帰ると、女の子のいた場所へ駆け寄ろうとした。 「だから邪魔にならないところにいて、っていったでしょう」 後方から声がする。振り返ると、槍の先に斧がついたような武器を片手に持った、例の女の子が立っていた。 「闘牛みたいなものよ」 魔物は、完全に頭を壁面に埋めて動かなくなった。衝突した衝撃で、崖からは郵便ポストぐらいの石が、ぼろぼろと落ちてきていた。見慣れない制服を着た女子高生は、力の抜けた魔物の後ろ姿を冷静に観察すると、素子に向き直った。 「あなた、神ヶ丘の生徒、よね」 「そう。今日から高等部に進学する、道成寺素子。あなたは?」 「私は、ソールズベリー魔科学院から魔術学園に転入してきた熊坂涼香。よろしくね」 「こちらこそよろし・・・」 素子は、抜刀すると正眼に構えた。 「また、来る」 涼香が振り返ると、さっきの魔物が、もがきながら頭を崖から抜こうとしている。ただ気絶していただけだったのだ。 「熊坂さん!止めは、ささないの!?」 素子の声は、いつもより上ずっている。 「刺さないんじゃなくて、刺せないの。私のレベルだと、強い攻撃魔法は使えないから」 魔物はようやく首を引き抜いた。 「素子!あなたの、あれは?」 「あれって?」 「あれよ、ほらあれ。あの、魔法の、アトリビュート!」 「あとりびゅーと?」 魔物は首を引き抜いたときに石垣から崩れ落ちてきた岩に狙いを定めると、素子たちへとぶつけてきた。二人は、別々の方向に避けた。うなり声を上げながら岩は二人の間を飛んでいった。 「なに、それ」 「あれよ・・・・属性!」 「火。ファイヤー!」 「わかった。じゃあ、私がやつを引き付けておくから、あなたが止めを刺して」 「えぇ!?」 「えぇ、じゃなくって、やりなさい!」 と言うと、涼香は意識を得物へ集中させた。 「シューティングウォータ」 槍の先から、水が弾丸になって次々と魔物に命中して、はじけていく。次の岩をふっとばそうとした魔物はたじろいだが、やはりトドメには程遠い。涼香は、絶壁側へと移動しながら正確に弾丸をヒットさせていった。 「ほらほら、こっちだよ」 目に水が当たるので、魔物は声のする方向へやみくもに突っ走っていく。 「いまよ!」 「ファイヤーボール!」 剣先に素子の身長ぐらいある火の玉が出現し、突進する魔物のわき腹へ抉るようにぶつかると、一瞬にして炎に包んだ。魔物は火だるまになりながら雷鳴の唸り声をあげて崖に突っ込むと、溶けるように消えていった。 「やった・・・」 素子は腰を抜かしたのか、その場に座り込んでしまった。実は、実際に魔物に対して魔法を使ったのは、これが初めてだったのだ。 「熊坂さん、やったよ」 「結構、やるじゃん。かっこよかったよ」 「あ、ありがとう。でも、一人だったら、絶対に封印できなかったかも」 涼香は燃え広がらないように、残り火を魔法の水で消した。 「あとは担当の人が来て始末するでしょ。ほら、立てる?」 「うん、多分」 涼香の差し出した手を握って、立ち上がった。 「じゃあ、神ヶ丘まで行きましょう。道、案内してくれるよね」 「うん。早く行こう、ってうわぁ!」 時刻、8時40分。 「遅刻だ!熊坂さん、はやく、走ろう!」 「素子、カバンは?」 「あ、カバンどこだっけ。あ、あそこだ」 素子のカバンは、坂道の途中に放り出されたままだ。 「はやくはやく!急いで」 素子たちが走り去った直後だった。白いセドリックが市街地方面から猛スピードで坂をのぼり、「現場」の前で止まった。 「俺たちが来る前に、こんなに派手にやってるとは、なぁ柴田!」 「そうですね。予想以上ですね」 車から降りてきたのは。揃いの黒いスーツに身を包んだ中年の男と若い男だ。柴田と呼ばれた男は、ブリーフケースの中から試験管を数本とビニール袋を取り出すと、周りに散乱している破片や、魔物の痕跡をいれていく。 中年の男は、まったく手伝うそぶりも見せず、タバコに火を点けた。背が高く、スーツの上からも、厚い胸板がわかる。そして、足元に落ちていた桜の枝を拾うと、道路にはいつくばっている若いのに言った。 「全く、今年の花見は台無しだな。なぁー、桜切る馬鹿、って知っているか」 「知っていますよ」 眼鏡をかけた顔を少しも上げずに返事をした。この、柴田と呼ばれた男も、中年男と同じくらいの長身だが、少し痩せ気味で、育ちのよさそうな柔らかな目をしていた。 「じゃあ、言ってみろよ」 「桜は、枝や幹を切ると、そこから腐ってしまう、という意味です」 「なんだ、おまえ本当に知っていたのか。さすがだな」 「それより、この穴についてどう思われますか」 崖にあいた二つの大穴を柴田が指した。 男は猛禽の目で一瞥した。 「体長5メートルから6メートル、一角系だろう。制圧魔法はおそらく火炎系。状況から見て、魔法を使ったのはおそらく二人。しかも、力はそれほど強くはない上、経験も少ない」 「そういえば、封印した人間がいませんね」 「なに、このあたりを片付けたら捜すさ。多分あそこだよ」 男は、手に持った桜の枝で、坂の上の「神ヶ丘魔術学園」を指し示した。 つづく | |