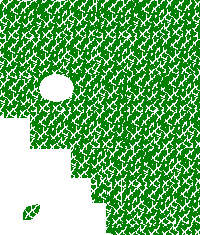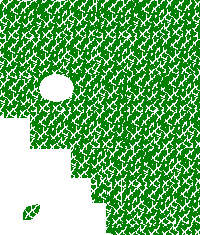|
改札口から出てくる人々は、いつ見ても水のようだった。水彩画のパレットを洗ったときのように色の混ざった水は、水門で少し淀み、吐き出されると階段を勢いよく下る。そして熱気でむっとする夜の街へ吸収され、跡形も無く消えていく。また電車が来る。それの繰り返し。ありふれた人々の風景。日本国中の都会なら、どこでも素晴らしいほどシステマティックに大量生産されている風景なのだ。
「見事なひかり具合だなぁ。でも、78点ぐらいか」
僕だって、あと3年ぐらい経ったら、あの濁った、酒や汗や香水やタバコなんかの臭いのする水の中の一滴になって、定年まで同じように止まることなく流されていく生活になるんだろう。しかも、夏休みのヒマをもてあました学生に、自分のはげ具合をマクドナルドの3階席から評価されながら。そう、こんなふうに。
「46点。で、若そうだからボーナスを+10点かな」
じゃあ、何の為に大学に入ったかといえば、このような人々の仲間に入る為なのだ。いや、それは受験勉強を始めたときから知っていたことだった。
知っていたって?いったい、高校生以前の僕は何を知っていのかい。大学に入ってから就職する、なんてこと現実感からいえば、――――チェックしておくポイントではあるけれど、特に今は関係が無いという意味では――――歴史年表の一項目と同じぐらいじゃないか。
「34点。頭頂部の密度に問題あり、か」
気になりだしたのは、前期が終わった後からだった。入る前は、大学ってのは頭の切れる人が大勢いる、もっとキラキラしたところだと思っていた。
別に、テレビドラマに出てくるぐらいの嘘くさいぐらいのキラキラは期待していなかったけど、高校の連中とは違う、もっと光っているヤツばかりだと思い込んでいたのだった。
「これは87点。本日の最高記録です」
このオジサンのような光りぐあいを期待していたわけではない。
でも、よく考えれば似たような高校から入学してくる、似たような学生ばかりだし、大学に入ったからといって人間が変わるはずもなく、よってキラともしているわけがない。エッシャーの騙し絵のように、ブレザーの制服が背広に変わってく過程でしかないのである。まさしく、僕は騙された。
ともかく、一人暮らしの僕の部屋にはエアコンが無い。このところ図書館が閉まった後は、こうやって1杯100円のシェイクだけでマックの二階で本を読むことにしている。もっと遅くなれば部屋の温度も下がるのだが、猛暑のおかげで、あまり涼しくもならない。節約とかエコとか考えずに、エアコンを付けてもいいかもしれない。買おうと思えばいつだって買える。なに、自分が付けなくたって誰かが付けるのだ。太平洋の島が沈むのは、僕だけの責任ではない。
さて、そろそろだろう。僕は、極限までふやけた紙コップのなかの、どろっとしたシェイクをすすって、ゴミ箱にぶちこむと、店を出た。大気がぬめりと沈殿している。排気ガスと汗とが肌にまとわりつく。出てくるのが早かったかもしれないと後悔したが、仕方がない。一晩中こうなのかもしれないし、このところの経験からするとそちらの可能性が高い。
住宅街に向かう並木道に踏み出したときだった。
男と目が合った。しわだらけでぺらぺらのスーツを着た、全体的に痩せてよれよれの中年男だった。暑いなら脱げばいいのに、着込んだジャケットの長袖をまくっている。不潔そうな、脂ぎった感じはしなかった。しわを伸ばさずに干した洗濯物のようだった。
彼はサングラスを下にずらして、僕を周囲の人間から識別した直後、ニタリと笑った。視線を絡み取られたような気がした。周囲に人がいることを忘れてしまうぐらい。でも、そんなに長い時間ではなかったはずだ。
男は、僕の視線を盗んだまま街路樹の手近な枝に触れた。瞬間、するすると消えるように、上っていった。まったく、不意の出来事だった。周りの人なんかも、一切気づかなかったと思う。まるで世界の、その部分に男が納まることが、何かの法則で定義されているような、そんな自然さで体が持ち上がり、跡形も無く葉の陰へと吸収されていったのだ。
ありがちなUFO特番の再現ドラマのような、垂直に吸収されていくような感じといえばわかるかもしれない。アメリカかどこかの農場主がUFOキャッチャーよろしくキャッチされて、地球土産の景品として連れて行かれそうになる光景を思い出してしまった。
我に返ったのは、サラリーマンが、入り口に立っていた僕を怪訝な顔で押しのけるようにしてマックに入ろうとした時だった。はっ。ははっ。冗談じゃない。街路樹といっても、電信柱ぐらいの太さもないエンジュの木だ。大人が猿でもあるまいし。そんなに早く登れるわけがない。
こんもりと白っぽい花をつけたエンジュの枝が、心なしか笑うように揺れた。ネオンに照らされて赤や青に見えた。
僕は、最初は控えめに、だんだん激しく幹を蹴ってみたり石を投げたりしてみたが、手ごたえは無かった。そのうち近くに止まっていたトラックの運転手が出てきたので止めた。木を通過した小石が、彼の車をたたきまくっていたからだ(知っていたけど)。
それから僕の毎日の習慣は、すこし変わった。場所や時間は同じなのだが、問題はその内容で、本を読んでいるふりをしながら、実際は窓の外側に見える並木道の観察(監視?)である。例の、あの男。UFO男と名づけていたが、そいつをまた見つけ出すことだ。再現性さ。科学というのは、再現されて検証されてこそ科学なんだ。現れなければ、夢か幻だ。仮にUFO男が現れたとしても、通り過ぎていけばなんて事は無い。やっぱり夢か幻なのである。
とりあえず、のつもりで二、三日はマジメに見張ることにした。その間、思わぬ収穫というか、予定外の因子というか、UFO男とはまったく違う男が、まったく違う木に吸い込まれていくのを見てしまった。しかも二人。一人は、若いサラリーマンで、安売り紳士服店に先週まで吊るされていたような背広を着、ナイロン製のカバンを持っていた。もう一人は、老人だ。カーキ色の帽子を載せた、丸っこい顔が笑っているように見えた。どちらも、木に吸い上げられて消えて行った。
「心霊スポット発見。人を飲み込む街路樹!?」
そんなことはない。人ごみの陰になって見えなくなった隙に、タクシーでも拾ったのだろう。気になってしまって、そう見えた可能性だってある。とにかくUFO男を見つけ出さなくてはならない。でなければ、せっかくマックに来ているのに落ち着いてマンガも読めない。もう一日、監視を続けた。それで来なければ、もっと窓際ではなく、奥の席で読めばいいことだ。
もう一日で止める予定だったが、どうしても気になり、一週間経った。カラスが黒いということを反証する為には白いカラスを連れてくればよい、という話を聞いたことがある。白いカラスを連れてくれば反証は楽かもしれないが、見つけて捕まえるのが骨だ。仮に見つからなくても、どこか別の場所、そう、自分の背中にでも止まっているかもしれない。まったく馬鹿げた話だ。
ただ、人もテレビ番組も、大抵一週間単位で動いている。あの男を見つけられないのなら、見つけられないのではない。そもそも居なかったのだ。
先週と同じ時間が近づいてくる。30分前に店の前に出て、往来を眺めておくことにする。いつものように、駅から吐き出された水の流れは、目の前の水路をたどっていく。その波間からUFO男を見つけ出さねばならない。
全く同じ時間だった。どこから合流したのか、先週と同じように現れた。人波をかきわけて、ヤツより先にエンジュの木に飛びついた。捕まえた、と思った。振り返ると、UFO男が立っていた。
「どうしたんだい」
黙っていた。
「別に・・・・」
「オレを捕まえてどうしようと思ったの?」
「・・・・・何のことでしょうか」
言い返すのが精一杯だった。男は、ふうと笑うと先週と同じように枝に触れようとした。
「おおかた、このまえの出来事が忘れられなかったんだろうと。違うかな?」
「まあ、それは」
「来るものは拒まず、違う世界に住んでみたいと思うなら。オレが上ったら、同じように枝に触れ。わかったな」
言うが早いか、UFO男は吸い込まれていった。
ここまできたら夢でも幻でもない。超常現象か、トリックか、もしくは幻視か幻聴か。科学は再現性だ。僕は、男の掴んでいた枝に触れた。
強烈なGが加わったかと思うと、何かの上に放り出された。落ち葉のような感触で受け止められた。球形の透明な膜の中にいるようだ。ネオンサインや駅、歩いていく人々が良く見えた。よく見えたが、音はあまり聞こえなかった。
男は、ポットからお茶を淹れていた。電気製品や家具類、クーラーまでも揃っており、外から見たよりも随分広かった。僕の下宿先よりも一回りほど大きいだろう。ということは、8畳くらいか。
「ここは、どこですか」
「木だよ。さっき見た」
「それは、そうですけど。こんな空間って、普通にあるんですか」
「さあ。でも、ここにはある。現に、オレもあんたもここにいる」
なんだか、妙に落ち着かない。まるで、初対面の親戚の家に預けられた子供だ。
「いつから、こんなところに?」
「ずっと前から。今のあんたと同じように、こうやって先人に導かれ、紹介されて。何の不思議もない。昔から、人は木の上に棲んでいたらしい。どれぐらい前からか分からないぐらい、ずっと前から」
お茶の入った茶碗を押し付けるように渡すと、男はテレビをつけた。
「電気があるんですか」
「ああ、あれですよ」
男が指差した場所では、枝が電線にからんでいる。
「この木は一等地なんだ。電気は使い放題。場所によっちゃケーブルテレビもネットもできる。もっともオレには必要ないから、別にいいけど」
野球中継を見ながら、男は背中を掻いた。何の為に僕を連れてきたのか。かまうようでもなく、かといってかまわないのでもない。あのしわしわのジャケットを着ながら、また横になって背中を掻いた。
「なんで、木の上に住むんですか?」
「家賃が只だから。快適だし、一等地だし駅から0分だしね。他にも、普通の勤め人だって、このあたりに住んでいるけど良いアパートを借りようと思ったら12万じゃきかないよ。只でこれなら、安いものさ」
「でも・・・・落ちたりとか、しないんですか」
「落ちたなんて話は聞かないな。特に、危険なことは無いよ」
全面ガラス張りの家、というものを想像して欲しい。しかも、中空にぶら下がっている。葉陰があるとはいえ、隙間からのぞくのは、ガラス越しに見るより良く見える町の風景だ。自分がどこに居るのか、どこを踏んで立っているのかよく分からない。
「あんた、名前は」
「古橋です」
「ふうん」
「あなたは」
「名前なんか、忘れたよ。エンジュの柏とよばれちゃいるけど」
「エンジュはわかりますけど、なんで柏なんですか」
「さあ。知ったこっちゃないさ・・・・。そういえば、いつまで居るつもりだい、あんた。帰らないのかい」
「はあ、帰れといわれてもどうやって帰ればいいのか」
「ああ、まだ教えていなかったか。そのあたりを・・・そうそう。ぐっと掴んだら地上に戻れる」
「そのあたりって、どのあたりでしょう」
「ここに住むなら、フィーリングが大切なんだよ。感覚さ。それがないやつには、いくら教えたって無理だ。あ、あのあたり、そうこの木が痒がっていると思うところを掴んだらいいんだ。それと、いつでも仲間になりたいと思えば、来たらいいさ。来る時のやりかたはわかっただろう?」
手当たり次第に床というか足元を掴むような動作を繰り返してみた。十数回やった後に、手ごたえがあった。体重を支える感覚がなくなり、無重力状態になるほど急激に落下したと思ったが、またマクドナルドの前に立っていた。
「UFO男は実在していた」
軽い興奮を覚えながら部屋にたどり着くと、今日一日熱せられてサウナと化した空気が迎えてくれる。まず、今日の調査は成功だ。だが、明日もトライしてから判断したかった。今日がまぐれだったということもある。一週間も張り込んだのだから、錯覚した可能性だってある。なかなか寝付けなかったのは暑さのせいばかりではない。
で、翌日。実は試さなかった。試す気が起きなかったのだ。何回か、図書館に行く前、マクドナルドに入る前、出た後、何度も前を通り過ぎたが、どうも枝を触ることができなかった。結局、そうこうしているうちに、夏休みも終わり、またぬるくて面白くも無い大学に通わなくてはならなくなった。
別に、必ず通わなければいけないこともない。出席なんてほとんどしなくても単位は取れる。現に、同じクラスの連中は、当番制で講義をやり過ごしている。でも、僕はほとんど出るしかなかった。いや、何か面白いことがあったら損だと思って。大学がつまらないところだ、というのを証明したくて全部出席していたのかもしれない。結局、白いカラスは見つからなかったけど。
キャンパスに銀杏の葉が溢れる頃、僕にちょっとした難題が持ち上がった。実家からの仕送りが止まった。詳しい事は言いたく無いけれど、出してもらっていた下宿代が、一切が払えなくなったのだ。授業料だけは何とか払ってもらえることになったものの、それまで自腹で払っていた食費やケータイ代に加えて部屋代も負担では、またバイトを一つ、増やさなければならない。大学生といえば、そこそこ忙しいわけで、バイトばかりしていられないし、かといってデイトレードで儲ける、なんてこともドンくさい僕にはできないわけで。
と思い出したのが、あの木に棲んでいる男。家賃光熱費ゼロの家だ。最初の日と同じように、マクドナルドの前に行って枝を探る。手ごたえは、まるっきり無かった。いや、たしか例の男は、木が痒がっているところを掴むと言っていたはずだ。
まわりを木にしながらも数回掴んでみる。なにしろ、家賃光熱費ゼロは魅力的だ。ちょうど12回目に手ごたえがあり、僕はあっという間に木の中へと吸い込まれていった。
エンジュの柏は、在宅だった。
あまり僕のことは覚えている様子ではなかったが、木の上に住みたい、と切り出すと手を叩いて喜んだ。で、彼に、あの木がいいんじゃないかとすすめられたのは、近所の「ふれあい公園」の中にある大振りなモミジ。バスケットコート1面分ぐらいしかない狭い公園なのだが、ちょうど隅のところに大きなモミジが生えている。公園が出来る前からあったようだ。
イチョウは臭いけど、モミジはにおわないし、秋はとんでもなく豪華になる。だけど、断った。モミジは冬になったら落葉してしまう。いくら外から見えないからと言っても、丸裸の枝に住む勇気は無い。できれば常緑樹がいいと思ったので、となりのキンモクセイにすることにした。これなら電線にも近いので、盗電も楽そうだ。
それから僕は、すこしずつ家財道具を運んでいった。
最初の頃は、周囲を気にして小さなものしか持ってこなかったが、意外とみんな注意を払わないらしく、段々と大きなものを持ち込むことにした。テレビ、パソコン、布団、冷蔵庫、リヤカーで運ぶと、ちょっとしたゴミ出しのようにも見える。新しい我が家に近づくと、キンモクセイの匂いでわかる。最近は、この匂いが染み付いたとみえ、大学の同級生からは「トイレの芳香剤のようなにおいがする」などと言われることもあるが、気にはしていない。
しばらくすると僕にも、少しでも大きい木には、確かに人の生活があることが見えるようになってきた。もっと大きな木には、たくさんの人がアパートのように、高さを分けあって住んでいる。
枝だけになってしまった木には、住人は居ないようだった。エンジュの柏に聞くと、冬になれば、みな常緑樹に住むようになるそうだ。落葉樹は、いわば別荘のようなものらしい。たいていの住人はモノを持っていないので、転居も簡単なのだが、僕は持ち物が多い。やっぱり、始めから常緑樹を選んで正解。
春になれば、やっぱり桜の木に引っ越す人が多い。花が散ったら、みんな自宅に戻るが、それまでは別荘として使っている。しかも、こんなに花見に適した場所があるなんて、木に棲むまでは知らなかった。
桜の木には、住人同士でルールがある。木は早い者勝ちで、棲み家を取った人は取れなかった人々を招待して、花見を行い、桜を見せびらかすのである。時々、風も無いのに桜の花が散ることがあるけど、あれは酔った招待客が木の中から揺らしているからだ、ということは僕も最近知ったこと。酒が足りなくなれば、眼下の酔客から少し、失敬すればいい。みんな気がつかないし、第一、人の家の桜を楽しんでいるのだから、それぐらいは貰ってもいいだろう。
棲み始めてから1年が経った。四季折々の生活。これほど都会にも自然があるということに、僕は気がつかなかった。風流というか、原始の生活というか、どこかで余計な力を入れてしまう、都会生活特有の緊張感が無い。それだけでも、大きな効果である。
久しぶりに駅前に出たとき、マクドナルドの前に棲んでいる柏氏を訪ねてみた。同じように枝を触って部屋へと上がってみる。
あいにく柏氏はいなかった。
帰ろうとしたとき、僕を呼び止める声が、壁のほうから聞こえた。よく見ると、柏氏が、木の肌にめり込むように座っている。
「どうしたんですか、柏さん。なんか、いつもと違うようですけど」
「いや、なんでもないんだ。なんでもない。ただ、『時』がきただけさ」
「時、ですか?」
「ああ、『時』だ。俺たち、木の住人たちは、時がたてば、いずれはこうやって木に取り込まれ同化していく運命なんだ。いわば、生物の共生だ」
「取り込まれるって、木に食べられてしまうんですか?」
僕はちょっと、ひざから先の力が抜けてしまっていた。
「似たようなものだが、少し違う。木は俺たちに住処を与えてくれる。俺は、ここ30年間、本当に快適に暮らせたんだ。だから、いずれは木と一体化していく運命だったんだ。まだこうしてオマエと話すことも出来るが、いずれはそれも出来なくなるだろう。俺の体は、このエンジュの栄養となり一部となる。魂も一部となる。それが自然の摂理さ」
僕がキンモクセイの木を出たのは、その9日後である。
|