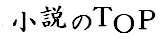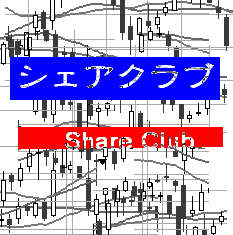 |
『シェアクラブ』 - The Share Club- |
|---|---|
瞬間湯沸かし器の羽田さんが、怒らなくなった。いつもは温厚なのだが、ちょっとしたミス(しかも、ほんとに些細な)でアルバイトの子を罵倒していた、あの羽田さんが、だ。これからは、こういうところに気をつけてよ。ただ、それだけ。まるで、落とし主にハンカチを拾ってあげるような感じで、しばらくは自分がミスをしたのか褒められたのか分からないぐらいだった。 おかしいのは羽田さんだけじゃなかった。同じ時期にバイトを始めたサヤも。3年ぐらい付き合っている彼氏が浮気をやめないとかで、ここ数日悩んでた。今にも、彼を刺して私も死ぬとか言い出すかもって、ずいぶん心配もしたし、昨日もかなり遅くまで電話で相談にも乗ってあげた。 でも、今日見たら、何事も無かったように「おはよう」って笑顔。よく、「憑き物が落ちたような」、って言い方があるけれど、最初から何も存在しなかったような顔なのだ。びっくりして聞いてみると、特に変わったことはないって。彼氏も心を入れ替えたとかじゃなく、同棲している部屋から出て行ったわけでもないらしい。気にしなくなったとか悟ったとか、そんな感じでもない。 「好きって気持ちが散らばっていったような感じかな。今でもすごく好きだし、でも、どうしようもないし、別れなきゃとも思っているんだけど、なんか全部が普通って感じなの」 「全部が普通って、状況に慣れちゃったんじゃない?」 「全然。慣れるなんて絶対にないと思う。でもね、彼のことも含めて全部が普通っていうか、好きってことも、すごく普通な感じがするし。昨日まではもっと特別な感じだった筈なんだけどね」 「でも、なんかあったんでしょう?」 「まあ・・・・ね。知りたいの?」 「当然でしょ。あれだけつき合わせておいて、メールのひとつもなしなんて」 「じゃあ、バイト終わってからね」 いつもどおりデータ入力をこなしていくサヤの横顔をチラッと見てみる。別に強がっているようにも見えないし、すごく幸せって感じでもない。別になんでもない、まさしく、正真正銘の普通といった感じ。普通は、「普通」とか返事をしてもうざくて言いたくないだけで実際は普通でもなかったりするんだけど、私が見ても普通に見える。 バイトが終わってから外に出ると、6時なのに真っ暗で、なんだか秋も過ぎていくような気がした。ちょっと歩いたところにあるパスタ屋で夕飯を食べることにした。 「で、何があったって?」 「何のこと?」 「あれだけ騒いでおいて、今日は平気だって?何も無いわけじゃないんでしょう?」 「そのこと、ね。そういえば、羽田さんって怒らなくなったでしょう?」 「はぐらかさないの。羽田さんなんて、関係ないでしょ」 「ううん。関係あるの」 「まさか、サヤ・・・」 「そういう関係じゃなくって」 サヤは視線をフォークに落とす。スパゲッティーをくるくると巻き取りながら。 「ね、ほとんどの人って、毎日毎日怒ったり笑ったり、とっても嬉しかったり、落ち込んだり、いろいろな気持ちになっているでしょう」 「うん」 「で、本当に落ち込んじゃったりしたらさ、ヤル気なんかなくなっちゃったりするし、怒ってたらいつもじゃ考えられないミスもしちゃう」 「そうだね」 「でもさ、いまこの瞬間にも、世界には心の底から楽しんでいる人だっているんだよね」 「そりゃ、そうだよ」 「なんか、不公平だと思わない?」 くるくる巻きのスパゲッティーをパクりと食べたサヤは、あまり不公平だとは思っていないようだったけど。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ シェアクラブとは、会員の皆様の間で感情のプラスマイナスをシェアすることで波を平均化し、リスク分散するためのクラブです。大抵の人間は、日々、喜怒哀楽を繰り返しています。ところが、その感情の波ゆえに普通の精神状態では考えられない行動を起こしてしまい、最悪の結果を引き起こしてしまうことがあります。当クラブでは、それを平均化することで、悲しみや怒りなどのネガティブな感情と喜びや楽しみといったポジティブな感情を会員間でシェアすることで感情の波を抑制します。このことで平常心を保ち、安定したパフォーマンスを維持するわけです。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ サヤのヴィトンから出てきたのは、A4のツルツルした紙だった。パンフレットっぽくなくて、シンプルというか、お金がかかっていないというか。これもまた「普通」としか言いようの無いシロモノ。 「ふうん・・・これがねえ。でも、不公平って言ったってさ、みんな良い時だって悪い時だってあるじゃん」 「良い時はいいけど、悪いときは本当に悪くなっちゃうよ。うれしくて死んじゃうって口では言うかもしれないけど、ホントに死んじゃうのは苦しいときだけだし。つまり、リスク分散っていうらしいんだけど」 「つまり、サヤも羽田さんも、このクラブの会員になったってこと?」 「うん。はじめはどうしようか迷ったんだけど、羽田さんが自分も入ってみて怒らずに済むようになった、心が軽くなったって言うから、ちょっと試しに入ってみたんだけど、わたしも気が楽になったというか」 「まあ、それはそれでよかったんじゃない、サヤが楽になったんだから」 普通に好物の明太子スパを食べながら、彼女は美味しいと普通につぶやいた。その一言は、ぽっと空中に浮かぶと薄く拡散して、すぐに消えていった。 | |