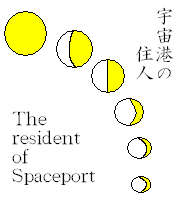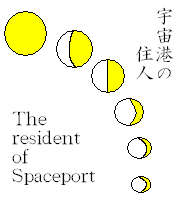私が初めてサイモン・Aに会ったのは、去年の12月だった。その日は随分寒くて、滑走路にもうっすら雪が積もっていた。だから、私はいつものように成田宇宙港ターミナル1のラウンジでホット烏龍茶を飲んでいた。
「隣に座ってもいいですか」
振り返ると、高価そうなスーツを着た北欧系の彫りの深い金髪の青年が、コーヒーを片手に立っていた。男でも見ほれるほどの、少女漫画から抜け出たような完璧な美男子だ。彼は私の返事を待たずに私の真向かいへ座った。
「お仕事ですね、ドクター」
彼の日本語には訛りが全く無い。日本人か、日本で生まれ育ったのかもしれない。オートラ(自動翻訳機)をつけている錯覚を覚えるほどだ。
「ええ。どうしてそれを。」
「あなたのスーツケースとズボンからはみ出たシャツを見れば分かります。それに半年に1回ここを通るのならなおさらね。」
確かに月面国際科学研究所へ半年ごとに出張している。だが、なぜこの青年がそれを知っているのか。
私はその時、専門家としての勘から、彼が高度な遺伝子操作を受けた人間であることを感じた。彼らの目の奥に漂う、独特の冷たさ。脳内チップ移植も受けているだろう。こういった先天的に技術的な人間には以前にも会ったことがある。
(もちろんこれら遺伝子組み換えは国連の倫理規約に抵触している)
「初めまして。私はサイモン・Aと申します。」
「サイモン・A?」
「そうです」
「A、 というのは?」
「A、 です」
「本名かい」
「そうです。本名です」
「変わった名字だねえ。どこの出身なの」
「・・・。火星」
火星植民が二年前の太陽電池大量破損のため頓挫したことは、かなり大きなニュースになった。
二十年前、火星の特権階級であった二十六家は、地球外に国家主権が及ばないことをいいことに独立した。火星にはレアメタル採掘による莫大な富があったからね。しかも各国は火星憲章の規約により武力行使できない。第一、「独立」なのだから、誰も対応することは出来なかった。
かくて二十六家は名字をアルファベットで一文字に改名し、王侯貴族となった。世界の金持ち番付の上位を占めて、栄華を極めていたのだ。
ところがその状況が変わったのが四年前だ。リサイクル新技術の開発により、レアメタルの価格が下落した直後、謎の事故により太陽電池の大半が使い物にならなくなった。太陽電池は地球からの輸入品だったが、地球は太陽電池を禁輸したので、やむを得ず植民者たちは地球へ帰らざるをえなかったというわけだ。当時からかなり陰謀説が流れていた事故で、さまざまな情報機関の関与が取りざたされていたが、今にいたるまで確かな証拠はない。
他の者は各国の政府や政治家に献金などをして国籍復帰、帰星が認められたのだが、サイモンはそれを拒んだと言う。国籍の無いものは帰星できない。よって四年も宇宙港内に暮らしているのである。
「じゃあ、君はずっとここに住んでいるのかい」
「はい」
彼の莫大な資産はスイスの銀行が管理しているから、望むものなら何でも手に入るし、会いたい人は誰でも呼び寄せることが出来た。高価なスーツ、美食、金。もちろん携帯とPCもある。ファーストクラスの個室ラウンジに住み、何不自由のない生活を送っている。
「でも、ほら、退屈しないかな」
「いえ、特に退屈するようなことはありませんが」
「外に出たくないのかい」
「そとって、地球のですか?」
「宇宙港の外さ。いろんなものがある」
「それぐらい、私も知っていますよ。ここは刑務所でもないし、タイムカプセルでもないんですから」
「それでも、毎日見るものは同じ景色、じゃないのかい」
「どこにいても人間の見る風景は毎日同じようなものです。違いますか、ドクターマツモト」
「だが自由がある」
「自由、ですか」
「人も大勢いるし、楽しいこともたくさんある」
「人が大勢いても、孤独な人は孤独だし、第一、豊かだから実感できないことだってあります」
私は、そのとき、多少むきになっていたのかもしれない。あまりにも彼が完璧すぎ、世間の苦労と隔絶していたからだ。努力もせずに人類の中で最高の肉体と頭脳を持ち、長寿と富を約束されている。彼になく、私にあるものは、このターミナルの外へと移動できる「自由」だけであった。
「友達はいるのかい」
「人のぬくもりは知らない方がいい。かえってつらくなるだけだから」
それを聞いて、私はすべて了解した。この若者の細やかな精神は、必死になって抵抗している。他人にとやかく言われなくても、彼自身が一番よくわかっていることなのだ。自分でもどうしていいのかが、分からないのであろう。ヒントを探して、ターミナルに集まる様々な人々に声をかけているのだろう。
そう思った私は、それ以上言うのを止した。かわりに、話を私のしている月の研究に移すと、彼は興味をそそられたらしく、私に玄人はだしの質問をした。時間はすぐに経ってしまった。
「もう行った方がいいですよ。搭乗時間は、あと五分しかない」
サイモン・Aは言った。
私はぬるくなった烏龍茶を一息に飲み干した。
「それじゃあ、また。2ヶ月後に、地球に帰ったら会えるかな」
「僕がここを出ていなければ」
彼は少し笑った。
「じゃ」
「メール、してもいいですか」
「いいよ」
見送る彼の眼は、私より遠くを見ていた。
月への定期便、去年から急に一般の客が増えだした。やはり月面の老人ホームが出来たからだろうね。
|