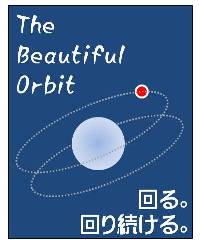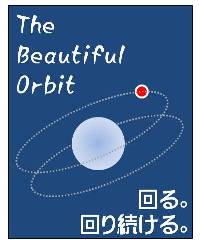|
月までの出張のついでに、軌道上の宇宙ステーションに併設された「アーティスト・イン・レジデンス」を見舞って、お土産を渡して欲しいと同僚から頼まれた。
アーティスト・イン・レジデンスとは、芸術家を住まわせて作品を作ってもらう、という企画のことを言うそうだ。あまり、芸術の方面には詳しくないのだが、
美術館や大学などではよくあることで、そこでしか作れないような作品を作ってもらうことを指す。さらに地元の人や学生・教授たちと交流してもらうことで、
芸術家側にもホスト側にもメリットがあるとのこと。
つまり、このケースではステーションに滞在する芸術家と研究者が相互交流することで、どちらにも良いインスピレーションを与えあう、ということを狙っているのだそうだ。しかし、宇宙のような滞在費が高額になるところでも開催するメリットがあるのか怪しいものだ。
それでも、頼んできた研究員は、研究所の中でも主に宇宙における人間の健康状態を研究しているセクションに勤めているのだが、軌道上に滞在していたとき
に、そのアーティスト・イン・レジデンスに暮らしている芸術家の一人と懇意になったというしい。宇宙基地では食べ物が限られているため、たまに、地上から
食べられるお土産を持って行くのが何よりも歓迎される。そこで羊羹を1本分託されたのだった。
月への便が出るまでには、まだ20時間と少しの時間がある。機が大気圏を抜け宇宙ステーションにドッキングを済ますと、その足で研究所の関連施設が入居している「きぼうⅡ」に向かった。
入居していると言っても、ステーションの規模からすると、それほど大きくはない。2世代ほど前のステーションの面影を残す「文化財」といった方が良い代物で、初代の「きぼう」の部品を流用している箇所もあるんじゃないかとジョークになるほどだ。
老朽化が進んでおり、スペースも電力の容量も大きくない。必然的に研究テーマも限られてきてしまうので新しい研究棟を増設したいのは山々なのだが、莫大な
予算が必要だ。新興宇宙ベンチャーのリサーチセンターに勝てるものといえば、長年培ってきた経験と勘、そして実際に長い時間が必要な実験ぐらいなもので、研究員の中には、民間に高額年俸で引き抜かれていくものもいる。やはりカネになる仕組みが出来ているところで、好きな研究を続けられるというのは、うらや
ましかった。(転職した後に「こんなはずじゃなかった」と言う者も少なくなかったが)
「きぼうⅡ」はAセクションとBセクションに分かれている。それぞれ「チューブA」と「チューブB」に研究室が十数個連結されている。アーティストインレジデ ンスは、Aセクションの中央にあった。扉を開けると、とてもか細い手足をした老人が、ペンを握りながら空中にさらさらと文字を書いていた。
「一閃」
という字が3次元データで書き上がると、彼は即座にネットワークにアップロードした。
「どちら様かね」
アップロードを終えた老人が、細く鋭い視線を投げかけた。
「足立に頼まれて来た、松本といいます」
「入りたまえ。ただ、あと5分待って欲しい。もうそろそろキリマンジャロの雪が見える頃だ」
眼下には大西洋らしい海が広がっている。雲の隙間から地上が見える。老人は、カメラをセットすると、地上を連写した。様々な角度で撮られたキリマンジャロの画像データをディスプレイにで確認すると、そのなかのいくつかをピックアップし、保存していった。
「春川です」
髭をピンと伸ばし、長い髪を後ろにまとめた顔を、こちらに向けた。意外に若いのかもしれないと思った
「足立から、差し入れを持ってくるように言われた、松本です」
「君か。足立君から聞いていたよ。ずいぶん早かったじゃないか」
「はい。到着してから、すぐ、こちらに向かいましたから。こちらが預かってきたものです。好物だと伺った羊羹です」
「ほう。羊羹か。喜んでいただくよ」
老人は、器用に手近な手すりをつかってこちらに飛んできたかと思うと、差し出された棒状の羊羹を受け取り、また自分の定位置に戻っていった。
「お礼といってはなんだが、さっき書いた新作を進呈しよう。送り先を教えてくれたまえ」
老人にアドレスを伝えた。くるくると空中で回転する「一閃」を見ながら、松本は近代的な設備と書道の対比を不思議に思った。多少古びているといえども、軌道上の宇宙ステーションだ。
老人は作品を送り終えると、さっそく羊羹をひとかけら、口の中に放り込んだ。
「うん。小豆から大地の匂いがする。緑、土、水。たまに地上のものを食べると、そうした普通の人間には分からないようなことに、気がつくようになるものだ。君は、今まで感じたことは無いだろう」
実際のところ、僕にも経験はある。
宇宙空間の植物工場製のものに比べると、ほんのかすかではあるが露天ものには「野趣」ともいうべき苦みがある。それが独特の風味なのだが、それは地上の空気を全く吸えない宇宙にいる時に、より鋭敏に分かるようだった。
「そうですね。なかなか分かりません。あまり宇宙に来たこともないので。ところで、先生の滞在は長いのですか」
「これだから新参者は困る。僕は、もう20年はここにいるんだ。知らない奴は、モグリだといっていい」
モグリか・・・。少なくとも、この業界には僕も20年ぐらいは居る。ただ、専門分野が細分化されてしまったために、あまり他分野(特にゲージュツ)には詳しくない。しかも、かなり話しづらい老人だ。話を変えることにした。
「先生は書道家なのですか」
「い
や、そんな専門バカではない。書道の他にも絵も描くし俳句、短歌、小説、映像、ありとあらゆる作品を作っている総合芸術家だ。おそらく、僕に匹敵すること
を出来る人間は、そうはいないだろう。現代人の悪い癖は、自分の興味のある分野や専門分野には異常に詳しくなるのに、他のことは簡単に調べれば済むと考え
ていることだろう。だがね、芸術も科学も、大元の所ではみんなつながった総合的なものなのだ。ルネッサンスの時代は、すべての芸術家がそれを理解してい
た。ここ20年間、ずっと研究施設の連中にも教えてきたのだがね。あまり浸透していないようだが、じきに価値が分かるようになると思っている」
僕は、早く話を打ち切って、レジデンスを出たくなった。シミの浮かんだ細い指に渾身の力を込めて、次の羊羹を切り取った。春川氏の指は、地上の同世代のそ
れと比べてみても細かった。筋肉の繊維が、ごっそり削りとられたような指だ。20年も滞在しているという彼の言葉を、指が証明していた。
「先生は、ずいぶん長く滞在していらっしゃるんですね。どうしてまた、そのように長くいらっしゃるんでしょうか」
「そ
れはね、芸術というのは奥深いもので、真理をつかんだと思った瞬間、するりと抜けてしまうからだ。いくら作品をつくっても、まだ芯を捉えることができな
い。たとえば、宇宙は季節感が全く無い。これが長所でも短所でもある。いや、窓から見る地球の様子で季節感はあるのだが、春風が吹いたり蝉が鳴いたりと
いった、日本古来の花鳥風月がないのだよ。だから、僕が、それに変わる新しい『風流』を考え出さなければ、日本の文化が真に宇宙に根付いたとは思えないん
だよ。その感覚を編み出すことが、僕のライフワークなのだ。だから、まだ帰るわけにはいかないのだよ」
そこまで一気に言うと、急に春川氏は短歌のアイデアが浮かんだようで、さっそく空中に流麗そうな文字で短歌を書き付けてみせた。
「こうやって、生活そのものが、すべて作品のクリエーションに繋がっていくんだ。地上では決して得られないインスピレーションを元に、ここ20年活動してきた。これは、他の芸術家では、決してまねできないことだと思う。専門バカには、この空間は勿体ないからな」
一方的に話をする春川氏に、僕は閉口していた。
暇乞いをすると、この会話は記録されているが、公開してもいいか聞かれた。特に話したこともないから、承諾しておいた。これも映像作品にするのだろう。
ただ、20年間も活躍しているアーティストにしては、奇異に感じていた。少なくとも、業界関係者である僕の耳に、春川氏のことが全く入ってこなかったというのは、いくら「専門バカ」だったとしても、考えにくい。しかも、あんな長期滞在なのに。
「やあ、松本さんですね。お久しぶりです」
帰り際に「きぼうⅡ」のオープンスペースに寄ると、知った顔の研究員がいた。
「おっ。そういえば、軌道勤務だったね、大塚さん。あと、どれぐらいで戻るんですか」
「あと、200日ぐらい。今回は長いんですよ。結構ミッションが残っているから、延長もあるかも」
「まあ、これから先、どれぐらい軌道上で研究が続けられるか分からないですからね」
「そうなんですよ。かなり予算も減らされていますからね。研究に直接関係のない一番大きいコストが地球と軌道上の往復ですから。そこを縮めようとするから、行けなかった連中の研究も僕が代行しているんです」
「じゃあ、さ。あの人も、そろそろ地上に戻らされるんじゃないですか?」
と私は、さっきまで居た春川氏のレジデンスに目をやった。
「ああ、被験者ですか。それは無いと思いますよ」
「被験者?アーティストでしょう」
「まあ、表向きはアーティストですが、私たちから見れば被験者ですよ」
大塚は肩をすくめた。
「どういうことですか」
「知らぬは本人のみ、なのか公然の秘密なのかは分かりませんが、春川氏は、低重力環境への長期滞在の実験の被験者なんですよ。もう、かれこれ20年は滞在していますから、連続滞在記録としてはトップでしょうね」
「でも、絵を描いたり書道や俳句、短歌、小説、映像、ありとあらゆる作品を作っている総合芸術家じゃないのですか」
「まあ、表向きはそうです。でも、松本さん、春川先生の作品は今まで見たことがありますか?無いでしょう。高額な滞在費に見合うだけの経済効果なんて、彼の作品にはないんです」
なるほど。
「そうは言っても、あまり先が長くない人を、なぜ地球に返さないのでしょうか」
「こ れには、大きく分けて二つの事情があります。一つは、彼のように10年単位で低重力下で過ごした人が大変貴重な存在だからです。彼がいることで、我が研究
所の宇宙医学部門は世界をリードできているといっても過言ではありません。重力や宇宙線、密閉空間から宇宙食といった環境すべてが与える骨や筋肉への身体面及び精神面への影響。けがや病気の予防と治療。どれも、トライアンドエラーで春川さんと一緒に実績を築いてきたといってもいいでしょう。もちろん、その
ためには春川さんに大きな代償を払っていただきました。それが2番目の理由です」
大塚は、視線を小さな窓の外に向けた。
「も う、春川さんは地球の重力に耐えられる体ではないのです。どんなにトレーニングや衣服、薬物を使っても、これほど長期にわたってしまうと影響を押しとどめるのは難しい。彼の体から得た知見で、今では今世紀初頭と比べたら低重力環境の影響を大きく抑えることが出来るようになりました。もし、春川さんが居なければ、私たちはそれこそ『筋肉トレーニングをするために宇宙に来ている』状態になっていたでしょうね。あなたの着ている発電と筋力トレーニングが同時に出来る、抵抗の入ったウェア。到着後に飲んだサプリメント。どれも彼の協力があったからこそ出来たものです。どちらも、私たち研究所の重要な『キャッシュカウ(金の成る木)』ですけどね」
被害者も加害者も、共犯ということなのだろう。おそらく、春川老人の作品は、どこかにアーカイブされているのだろうが、それは「芸術」として保存されるのではない。きっと、それらは精神状態を分析する格好の「研究材料」なのだ。
「それに、もともと芸術家なんかじゃないんですよ。全財産を使って宇宙に来たものの、帰りたくなくなって潜んでいたところを、捕まったのが発端です。ちょうど、長期滞在の観察をしようと計画を立てていた某教授が、春川氏を保安部から請け出してきてアーティストとしてレジデンスに住まわせたんです。だから、いま地球に帰ったところで、どこにも行き場所はないんですよ」
大塚と別れ、月行きのラウンジで時間を潰すことにした。『コーヒー』のパックを買い、壁に体をマジックテープで固定した。様々な人が行き交うターミナルを
見ながら、コーヒーの香料が入った色つきの苦い飲料の玉を口の中に含んだ。適度にぬるい。手元の端末を開くと、先ほど春川老人が描いていた「一閃」という書が、ようやく転送されてきた。
窓から次の朝日が、ぬるぬると上がってきた。
|